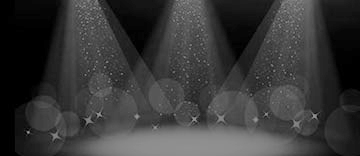記事の中にある「(スピーカーマーク)」をクリック/タップで音声を聞くことができます
-
Photo by Kondo Atsushi
-
「大事なのは作品であって、自分の個性や作家性なんてどうでもいい」
前田哲 #2
今回のアチーバーは、映画監督の前田哲さんです。前田さんは、19歳で東映東京撮影所で、大道具のアルバイト、美術助手を経てフリーの助監督となりました。伊丹十三監督、滝田洋二郎監督、周防正行監督らのもとで経験を積み、1998年に相米慎二監督のもとで、オムニバス映画『ポッキー坂恋物語 かわいいひと』で監督デビュー。2018年公開の大泉洋さん主演映画『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』のヒットで注目を集めると、その後も『そして、バトンは渡された』『老後の資金がありません!』など話題作を手掛けてきました。「遅咲き」と語るキャリアから見えたチャンスのつかみ方、理想とするリーダー像、人の心を動かす極意とは―。今回は全3連載の2回目です。
Q:ビジネスの世界にも通じますが、大事な場面でいかに結果を残せるかは成功への重要なポイントです。前田さんにとっては、2018年の『こんな夜更けにバナナかよ』のヒットがキャリアのターニングポイントだったように思います。
大げさに言うと、人生を賭けたというか、監督生命を賭けたということですね。当時、『ボヘミアンラプソディ』が大ヒットしていて、年末公開の作品がない中、12月28日に公開したんです。映画は最初の3日間で勝負が決まると言われているんですけど、全くダメで、数字を聞いた時には、「あぁ、終わったな」と思いました。ただ、普通はどの映画も2週目、3週目と数字が落ちていくんですけど、2週目から上がっていったんですよ。それは本当に映画の力で上がっていったんだと思っています。それで、僕の中では首の皮一枚残ったっていう感じですね。やっぱり数字が出ないといけない。興行収入が10億を超えたので、今ここに座われているのだと思います。
Q:筋ジストロフィーの男性を主人公とした難しいテーマの作品です。どのタイミングから手応えや、成功のイメージがあったのですか?
ノンフィクションもの、実話ものが流行ってはいましたけど、主人公が障がい者ということもありましたし、売れている本でもなかったので、企画のハードルは高かったんです。スターが必要でした。大泉洋さんの出演が決まりました、そして、高畑充希も決まりました。それでも製作のOKが出ずに「もう1人主役がいります」って言うので、三浦春馬くんに来てもらった。3人の主役級を並べて、やっとGOが出たという感じでしたね。Q:前田さんにとって「勝負」のこの作品で成功を収められた要因はどこにあるのでしょうか。
僕自身は変わってないんですけどね。結局、企画とタイミング、それと何よりも俳優さんの力ですよね。俳優さんも組み合わせで、この人とこの人が組んだ見慣れた2人がいいという場合もあれば、「この3人で何が起こるの?」って見え方が大きいこともあるんです。映画を見ずに、後から配信とかDVDで見たらすごく面白かった時ってあるじゃないですか。何で映画館で見なかったんだろうって。映画って不思議なもので、「見て良かった」ではダメで、見たいと思わせなきゃダメなんですよ。みんな必死で作ってるんだから、「見てよかった」作品はいっぱいあると思うのです。それでいうと本当にタイミング、俳優さんとのその組み合わせの力、それらと作品との相性・・・いろんな奇跡が起こった時に、映画が力を持つんだと思います。Q:過去に大きな予算の映画で監督をすることになった時に、数字的な成功を追い求めて失敗をしたという話がありました。「バナナ」と向き合うにあたり、同じ失敗を繰り返さないために何か意識したことはあったのですか?
それまでの失敗は、「監督」っていうポジションを意識し過ぎて、自信満々でないといけないとシャカリキになっていた部分があったと思うんです。それは年齢的なこともあるかもしれないし、キャリアの問題かもしれないですけどね。バナナの時は「後がない」と、いろんな意味で開き直って「みんなで作っている」って事をもう一度思い直して、人に任せる、人を信頼するっていうことを考えました。それまでは、助監督をやってきているので、「仕事をやるのは当たり前でしょ」「作品に全部捧げて当たり前でしょ」っていう意識があったんですが、あるプロデューサーから「監督、ありがとうが少ないよね」って言われたんです。当時は「みんなプロフェッショナルで、仕事でやってるのに何でいちいちありがとうって言う必要があるの?」って思っていたんですが、「いや、そうじゃないな」と。それも分かるなと感じたんです。
Q:周囲に対する考え方に変化があったのですね。
監督って何もできる立場じゃないんですね。音を取るわけでもない、演じるわけでもない、全部スタッフが何かを用意してくれるわけで、朝の5時に起きて荷物を積んで運んでるスタッフがいるから現場が成立してるわけです。それを自分がやってきたから、どこか当たり前だと思っていたんですけど、そうじゃないわけですよね。だから、「ありがとう」を言うようにしたんです。「ありがとう、ありがとう」って。最初はもちろん機械的ですよ。でも、不思議なもので、最初は機械的に言ってたものが、心の底から言えるようになってきて、自分でも腑に落ちたんです。その時に、形から入って何も悪くないんだということをすごく学びましたし、向こうがどう思っているかは分かりませんけど、今、自然に「ありがとう」って言えているのが、自分の中で本当に心の底から言えて気持ちいいんですね。Q:「形」を変えることで見える景色にも変化があったと?
そうですね。映画も結局は同じことで、自分を疑うではないですが、単に自分の好みになってないかってことが大事なんです。知らない間に同じパターンに陥るし、それが楽だから自分の得意な形に入っていくんですよ。だから、僕は自分の映画を見直さないですし、全部0ベースで、毎作品、毎作品違うんですよ。物語が違うわけですから。だから僕の映画のスタッフは「前田組」っていう固定がないんです。毎回違う人と刺激受けてやってもらっていることが多いですね。Q:監督は映画制作の「リーダー」です。前田さんは組織をまとめる上で、どのようなことを意識していますか?
リーダーだからこそ、旗を持って引っ張っていかなければいけない中で、強制力だったり、強い力は必要な部分だと思いますが、今の時代、そうじゃないやり方もあるんじゃないかっていうことですよね。僕らは、叱られて育ちましたし、「ちくしょう、負けるもんか」って思って頑張ってましたけど、今は相手を乗せることがリーダーに求められていると思います。
Q:そうした考え方は、演出の面にも表れているのですか?
俳優さんに対しても、一緒に考えるって事ですよね。ああしてください、こうしてくださいって言うのが僕は演出だと思ってなくて、場を与えることだと思ってるんです。強制したり、こういう役だからこうとはめ込むんじゃなくて、「ここの感情はそういうパターンもあると思うんですけど、違うことも考えられないですかね」と一緒に考える。簡単なことで、「右向いて」って言ったら右を向けるし、こういう台詞って言ったら、そのまま自分の言葉のように言えるんです。でも、そうじゃなくて、彼らが右を向くまで待ち、彼らが本当に心の中から言葉が出てくるのを待つんですよね。自分で考えて思いついて、行動することが一番リアリティーがあると僕は思っていて、僕の演出論はどっちかというとそっちですし、僕は芝居はリアクションだと思っているので。彼が演じたこと、やったことで彼女がどうリアクションを取るかっていうのが一番自然じゃないですか。それを毎回望んでいますね。Q:リアクションによって、前田さんの想定外であっても構わないと?
映画は生き物なんですよ。絶えず変化していくっていうのが僕の考え方で、僕が例えばBというイメージを持っている時に、Aっていうイメージを出してくださった時は、ぶつかっていいと思ってます。ぶつかるとみんな「相性が悪いのかな」と言うけど、ぶつからないとわからないし、一番楽しいのはAダッシュになる時でもBダッシュになる時でもなくて、ぶつかったことでCという全く違う発想が出てくる瞬間ですね。僕は、それがモノづくりの醍醐味だと思っているんです。どんなプロジェクトもそうだと思うんですけど、別に妥協してるわけじゃなくて、高めていって、何か全く違うものがポンと降りてくる瞬間が面白いですし、それは奇跡かもしれないけど、ぶつかるからこそ生まれてくることだと思っています。
Q:そうした瞬間、瞬間の判断をしていくには何が必要ですか?
大事なのは、僕がスタッフ、キャストに対するときに、自分なりのちゃんとした答えを持っているかということです。それは正しい、正しくないじゃなくて、この映画にとってどうなのかってことですね。それは映画が決めていくことだと思っていまうし、映画は生き物だからこそ、そこに自分の趣味が入っちゃいけないと考えています。Q:映画監督というとこだわりが強いというイメージがありますが、前田さんは柔軟さを大切にしていて、変化を楽しんでいるようにも感じます。
よく陶器に作られた方の銘とか入ってるじゃないですか。僕が目指すのは日常使いの器、茶碗とかコップなんです。僕が見て育ったエンターテイメントのハリウッド映画とかは、見やすいものです。誰に対しても垣根がなくて、どの世代も見やすくて入りやすい。なので、誰々の作というブランド名が入ってないけど「なんか持ちやすいよね、これ」「使いやすいよね」っていうのが作り手として僕が目指すところですかね。日常使いのものってそうじゃないですか。「用の美」という言葉もありますが、誰しもが手に取って使いやすい、気軽に見れる、そういう映画を作りたいと思っています。Q:大事なのは自分の存在を際立たせるのではなく、映画の魅力が伝わるかとどうかなのですね。
大事なのは作品であって、そのために自分の個性とか、自分の作家性なんかどうでもいいってことなんですよね。ただ、消そうとしても出ちゃうんですよ。その人を演じるのと同じことだと思うんで、やっぱり滲み出ちゃう。なぜかというと、それがその人の生きてきた人生だし、その人の人生に対する考え方なので。だから恥ずかしい生き方できない、と常日頃思ってます。そんな正しい生き方をしているわけじゃないんですけどね。前田さんの「THE WORDWAY」。次回♯3は、前田さんが映画を通して伝えたい思いを語ります。上手くなくても、得意でなくてもいいー。夢を引き寄せる「言葉」を感じてください。
 THE WORDWAYでは、読者から、アチーバーの記事を読んだ感想を募集しています。記事を読んだ感想、「昨日の自分を超える」トリガーになったこと、アチーバーの方々に届けたい思いなど、お送りください。いただいたメッセージは、編集部から、アチーバーご本人に届けさせていただきます! アチーバーに声を届ける
THE WORDWAYでは、読者から、アチーバーの記事を読んだ感想を募集しています。記事を読んだ感想、「昨日の自分を超える」トリガーになったこと、アチーバーの方々に届けたい思いなど、お送りください。いただいたメッセージは、編集部から、アチーバーご本人に届けさせていただきます! アチーバーに声を届けるPROFILE
- ◆前田哲(まえだ・てつ) 東京東映撮影所で大道具のアルバイトを始めて、セット付き、美術助手を経て、フリーの助監督として伊丹十三、滝田洋二郎、大森一樹、崔洋一、阪本順治、松岡錠司、周防正行らの作品に携わり、1998年相米慎二総監督のもと、オムニバス映画『ポッキー坂恋物語 かわいいひと』で劇場映画監督デビュー。主な作品に『ドルフィンブルー フジもういちど宙へ』(2007)、『ブタがいた教室』(2008)、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』(2018)など。2009年度より、東北芸術工科大学デザイン工学部映像学科准教授を務め、2013年に退任。2021年には『老後の資金がありません!』『そして、バトンは渡された』で報知映画賞監督賞を受賞。2023年は『ロストケア』『水は海に向かって流れる』『大名倒産』が連続公開。次回作は、直木賞をはじめ数々の賞を受賞し、今年11月5日に100歳を迎える作家・佐藤愛子氏のベストセラーエッセイ集を実写映画化した「九十歳。何がめでたい」。女優・草笛光子が自身と同じ90歳の作家を演じる話題作で、24年6月21日公開。
HOW TO
THE WORDWAYは、アチーバーの声を、文字と音声で届ける新しいスタイルのマガジンです。インタビュー記事の中にある「(スピーカーマーク)」をクリック/タップすることで、アチーバーが自身の声で紡いだ言葉を聞くことができます。 CATEGORY
Top Achievers from other areas are also on the way. Stay tuned!! IMPRESSIVE WORDS
RECOMMEND
あわせて読みたい
-
-
-
「何かを変えるために必要なのは続けること。短期的な下心では何も変えられない」
羽根田卓也 #3
-
-
-
-
「アピールは成長のために必要。出会う人の数が増え、新しいことを知るチャンスも増える」
田中史朗 #3
-
-
-
-
「環境に飛び込まないと、できるかできないかは分からない。でも、飛び込まない限り確実にできない」
田村大 #2
-
-
-
-
「何かを変えることが人生の喜び。僕にとっては、それがたまたまカヌーだった」
羽根田卓也 #1
-
-
-
-
「挑戦するときに知識はいらない。パッションとエナジーさえあればボールは動く」
大神雄子 #2
-
-
-
-
「気持ちのままに突き進むことで、行動がついてきたり、変わってきたりする」
上田桃子 #1
-
-
-
-
「実力不足だと分かっていても、自分からは絶対に言わない」
永田裕志 #1
-
-
-
-
「気合い、根性は必要だけど、後でいい。まずは楽しんで、挑んでいくこと」
矢野燿大 #3
-
-
-
-
「チーム全員でアウトプットして作った目標なら、全員でそこに向かっていける」
大神雄子 #3
-
-
-
-
「どうせ立ち向かうなら、楽しく立ち向かう。筋トレと同じで、つらい環境が筋肉になる」
楠本修二郎 #3
-
-
-
-
「チャンスはピンチ。それをモノにできなければ、また1から始めるしかない」
前田哲 #1
-
-
-
-
「行動をまず変えないと、変わらない」
澤村拓一 #3 (メジャーリーガー)
-
-
-
-
「辞めるかどうかを決めるのは人ではなく自分。その思いがあったから、やって来られた」
岩澤 資之 #2
-
-
-
-
「『ここだけは絶対に負けない』という強いものがあるから、他の事で負けても悔しくない」
澤 穂希 #1
-
-
-
-
「苦しさがあっても、そこから逃げられないのなら、その中で楽しめばいい」
西高辻󠄀 信良 #3
-
-
-
-
「夢をつかむ一番は明確な意思。漫然とやっていては時間もかかるし、パワーもなくなる」
岩澤 資之 #1
-
-
-
-
「寝る前に鏡を見て、「自分の力をすべて出したか」と聞く。それに答えられないのなら引退した方が良い」
トム・ホーバス #3
-
-
-
-
「思っているほどは、誰も自分に期待していない―。そう思えば楽になる」
潮田玲子 #2
-
-
-
-
「「もう無理」と思っているところから、自分で何か良い部分を見つけ出して成長し、そして限界を突破する」
田中史朗 #1
-
-
-
-
「やりたいことがないというのは、甘え。やりたくないことを、やらないでいい努力をする」
ハリウッドザコシショウ #2
-
-
-
-
「三振は三振でいいけど、見逃し三振だけはしたくない」
ハリウッドザコシショウ #1
-
-
-
-
「不安になったら『澤穂希はできる!』と自分に言い聞かせて行動に移す」
澤 穂希 #2
-
-
-
-
「チームは盆栽と一緒。毎日きれいにカットしなければ、おかしくなる」
トム・ホーバス #2
-
-
-
-
「『日々成長』―。何か成長したければ、結果失敗しても、最終的にたどり着きたいゴールには近づいている #4」
上田桃子 #4
-
-
-
-
「選択肢がある時に迷いが生じるのは当たり前。大事なのは自分が選ぶこと」
深浦康市 #3
-
-
-
-
「誰かが通った道は歩きやすいが、何も残っていない。誰も通っていない道は歩きにくいが、多くの世界がある」
羽根田卓也 #2
-
-
-
-
「変わっていく勇気は必要ですが、変わらない信念も必要なんで」
澤村拓一 #2 (メジャーリーガー)
-
-
-
-
「ビジネスのこだわりは、好きなことしかやらないこと、自分だけが勝たないこと」
たむらけんじ #2
-
-
-
-
「自分だけがいい思いをしてはいけない。師匠、先輩から受けた恩は後輩に返せばいい」
岩澤 資之 #3
-
-
-
-
「大きな目標に到達するために、目の前の先輩を抜こうと思ってやってきた」
オール巨人 #1
-
-
-
-
「不正解、エラーを取り除くことは、完璧なパフォーマンスを出そうとするより大事」
村田諒太 #2
-
-
-
-
「こだわりを通して仕事にしたいのなら、人の倍やらないと成立しない」
梅原大吾 #3
-
-
-
-
「螺旋階段みたいなもの。歩みを止めなければ、回っているようで、少し登っている」
渡部暁斗 #2
-
-
-
-
「何か物事を達成したければ絶対に諦めない」
青木宣親 #3
-
-
-
-
「本当に強い人間は、転んでも必ず立ち上がって、堂々と前を歩いていく人間です」
永田裕志 #3
-
-
-
-
「不安やネガティブな事をもっと共有していれば、もう少し自分たちを信じて戦えた」
潮田玲子 #3
-
THE WORDWAY ACHIEVERS
隔週月曜日に順次公開していきます
IMPRESSIVE WORDS
LATEST WORDS
最新の記事
-
-
-
「何か物事を達成したければ絶対に諦めない」
青木宣親 #3
-
-
-
-
「「取り組み方」と「考え方」が1日の流れを決める。それが1年、2年後につながっていく」
青木宣親 #2
-
-
-
-
「結果が出ないことをメンタルのせいにしているから、同じことを繰り返してしまう」
青木宣親 #1
-
-
-
-
「アピールは成長のために必要。出会う人の数が増え、新しいことを知るチャンスも増える」
田中史朗 #3
-
-
-
-
「言葉に出すことはすごく大事。言葉で相手を引っ張ってあげることもできるし、しんどさを楽しさに変えてあげることもできる」
田中史朗 #2
-
-
-
-
「「もう無理」と思っているところから、自分で何か良い部分を見つけ出して成長し、そして限界を突破する」
田中史朗 #1
-