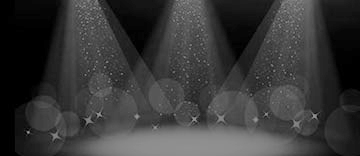記事の中にある「(スピーカーマーク)」をクリック/タップで音声を聞くことができます
-
Photo by Kondo Atsushi
-
「チャンスはピンチ。それをモノにできなければ、また1から始めるしかない」
前田哲 #1
今回のアチーバーは、映画監督の前田哲さんです。前田さんは、19歳で東映東京撮影所で、大道具のアルバイト、美術助手を経てフリーの助監督となりました。伊丹十三監督、滝田洋二郎監督、周防正行監督らのもとで経験を積み、1998年に相米慎二監督のもとで、オムニバス映画『ポッキー坂恋物語 かわいいひと』で監督デビュー。2018年公開の大泉洋さん主演映画『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』のヒットで注目を集めると、その後も『そして、バトンは渡された』『老後の資金がありません!』など話題作を手掛けてきました。「遅咲き」と語るキャリアから見えたチャンスのつかみ方、理想とするリーダー像、人の心を動かす極意とは―。今回は全3連載の1回目です。
Q:それでは宜しくお願いします。前田さんは19歳で映画の世界に入ったそうですが、まずは映画監督を志した経緯を教えてください。
僕が小学生の頃はテレビでゴールデン洋画劇場や日曜洋画劇場、水曜ロードショーなどがあって、映画の世界への憧れがずっとあったんです。どちらかというと、ハリウッドの映画ですね。スティーブ・マックイーンというスターがいて、次の日に学校で友達と見た映画のワンシーンを演じるわけです。みんな運動場でボール遊びをしてるのに、机を並べて、トンネルから脱走したり、ほうきを銃の代わりにしたりするのが楽しかったですし、ハリウッドのスターたちが取り上げられる「スクリーン」と「ロードショー」という雑誌が愛読書でした。Q:映画を「見る」ものではなく、「作りたい」と思うきかっけはあったのですか?
当時、アメリカの『LIFE』という雑誌の映画の部分ばかりを抜粋した、大きくて、高級な紙質でツルツルとした『LIFE GOES TO THE MOVIES』という本があったんです。友達が持っていたその本を僕も欲しくて、お年玉を貯めて買いました。それを見ると、スターだけじゃなくて映画の裏側、いわゆるスタッフ側の作り手たちがいっぱい載っていたんですね。当時は監督とプロデューサーの区別もつかないんですけど、大きなクレーンがあって、そこにカメラが乗っていてそこを覗いてるカメラマンがいる。そういうのを見ていて、こっち側の人間になりたい、映画の作り手の方に参加したいと思ったんです。映画界に入るんだと自分の中で決めたのが、小学校4年生の時で、卒業文集には、みんな社長になるとか、博士になるとか書く中で、なぜか野球帽を被ってインカムをつけて、カチンコを持って、「映画プロデューサーになる」と書きました。映画の世界に入って一番偉い人、そういう発想の中で、作り手の重要なポジションに就きたいっていう思いが、小学校の時に芽生えていましたね。
Q:誰しも幼い頃に夢を抱いたり、憧れの職業があったりしますが、夢を追い続けることは簡単ではありません。前田さんが映画監督という夢を実現できたポイントはどこにあるのでしょうか。
1つはやっぱり好きだからってことですよね。好きだから続けられるし、夢中になれる。夢中になれるっていうのは、字のままで夢の中じゃないですけど、集中している時の気持ちよさですよね。他のことを考えなくていいし、嫌なことも全て忘れて没頭できるって事だと思うんです。もう1つは、「つぶし」がきかなかったということです。僕は19歳の時に、東映東京撮影所にアルバイトとして入って、その後、助監督を担ったんですが、助監督だけでご飯を食べていくのはなかなか厳しい世界、時代でした。仕事はフリーランスですから、仕事が来れば良いですけど、間が空いたりもする。実際、その間にアルバイトをしようとして、そのままそっちの世界に行ってしまう同世代の仲間もたくさんいました。僕はたまたま巡り合わせが良かったのか仕事が続いてくれたのと、他のことが上手にできなかった。他の道に引っ張られなかったとも言えますね。助監督になるのも時間がかかったんですけど、そういう意味で「つぶし」がきかなかった。その2点かなと思いますね。不器用だったのが幸いしました。Q:アルバイトや助監督時代の経験で、今に繋がっていることはありますか?
人との巡り合わせの大切さですね。当時はCMの世界、テレビの世界、映画の世界は、今ほど自由に行き来できなくて、スタッフもテレビ、CM、映画の人って分かれていたんです。僕がこの世界入った頃はちょうど過渡期で、だんだんCMのデレクターやテレビの演出家が映画を撮り、テレビ局が映画に出資だけでなく企画製作するという流れができはじめていた。もちろん、映画の世界に行きたいわけですから、いかに映画のスタッフと知り合うかが大事なんですが、僕は助監督のときにCMの制作に呼ばれ、CMのプロダクションと知り合えたことが、CMから生まれたオムニバス映画『ポッキー坂恋物語 かわいいひと』(98年)での監督デビューに繋がったんです。映画界でデビューできたわけじゃなく、CM界が背中を押してくださった。そういう流れがありましたね。
Q:夢につながる道は一通りではないということですね。
そう思います。デビューする時もどっちかを選ぶタイミングがあったんです。松竹さんが新しい映画を作り始めるっていう動きがあって、そこで一回助監督についたら監督デビューできるという話と、先ほどのオムニバスだけど1本監督をできるっていう話が同じ時期にあって、どっちを選ぶかだったんです。助監督を1本やって監督って、話はいいけど保証はないなとか色々考えて、こっちを選ばせてもらったっていう。そういう分岐点はありましたね。Q:前田さんのキャリアを振り返ると、1998年に監督デビューを果たした後はヒット作に恵まれない時期が長く続きました。「こんな夜更けにバナナかよ」(2018年)のヒットまで、諦めそうになったり、映画との向き合い方に変化はありましたか?
10周遅れなのか、20周遅れなのかわからないですけど、半分揶揄で半分褒め言葉で「遅咲きだね」ってよく言われます。『こんな夜更けにバナナかよ』の4、5年前まで、13本、インディーズ、メジャー含めて毎年映画を撮ることができていたのですが、メジャーで3回も興行的に失敗してる人は僕ぐらいじゃないですか。普通は1回失敗したら2度目のチャンスはなかなか訪れない。ただ、なぜかチャンスが巡ってきて撮らせていただいて、またヒットしない。この世界、興行成績というのは非常に大事で、数字がない人間がまたチャンスを頂けたのに、また失敗したという申し訳ない状況が続いてました。Q:結果が出ず、2009年から13年までは東北芸術工科大学で学生に指導していた時期もあったと聞きました。監督として映画が撮れない5年間というのは、どのようなものでしたか?
すごく苦しかったですね。ですので『こんな夜更けにバナナかよ』に集中するために大学も退任して、それに全てを賭けました。興行成績がちゃんとフィットすることを全身全霊で目指そうと。10億円を超えるってのいうのは1つのメジャー作品のラインなので、いい映画、観客が見て面白いものを目指して作るのは当たり前のこととしても、ヒットする、しないと別のモードはあるわけです。制作まで3年半かかったんですが、それに全てを賭けて、大学も辞めて、収入も全部なしになったところで、人生の勝負ですね。これが興行成績もダメだったら、映画の評価もダメだったら監督は続けられないという覚悟もありました。
Q:結果としてはすべてをかけた「バナナ」が大ヒットし、監督としてのターニングポイントとなりました。3回の失敗を経験したということですが、結果が出ない時は何が足りなかったのだと思いますか?
予算が4000万円レベルの映画を撮ってきた時に、いきなり3億円近い予算をかけた大きなメジャー作品のチャンスが巡ってきたことがあって、恥ずかしながら、自分の中で「これで名前が売れる」という邪心があったんです。その時に、一生懸命映画を作るんですけど、その大きな現場をうまく仕切れなかった。それまではプロデューサーと二人三脚だったのが、プロデューサーが5人も6人もいて、みんな言うことが違う中で、自分が見えづらくなってきて、興行成績も全く伴わなかった。その時に、先ほどの邪心も含めてどこか自分に嘘をついていたなと気がついたんです。 成立させるために、自分に嘘をついて作るっていうことが一番苦しいことで、その時にもう終わったなと思いましたね。自分に問うたわけです。「何がやりたいの」って。「有名になりたかったの、あなたは」「お金を儲けたかったんですか」って。「違うでしょ」と、「映画が好きなんですよね」って。そしたら、「映画が好きで、大きい小さいじゃなくて映画に携われることが自分にとっての幸せであって、映画と真摯に向き合うことがあなたの一番望んでることじゃないのか」というところに落ちたんですよね。名声が欲しいとか、お金が儲かる、ちょっと幸せにお金が増えるのかなっていう邪心が一番良くなかったんだなと気づいたんです。そこは、自分の中ですごく反省した部分ですね。Q:その苦い経験が、前田さんの映画監督として目指す方向性を明確にしたと??
そう思います。大きなプロジェクトになると、当然ですけれども他のことが目に入るわけです。ただ、監督にとって一番大事なことは映画と向き合うことで、現場、俳優さんと向き合い、スタッフと向き合って映画をよくするためだけに集中しないといけない。それを違うところが見えてきて、「これはヒットするんじゃないか」「大きいプロジェクトだから、すごい宣伝するんだろうな」とか、そんなことは本当は関係ないわけです。もちろん、映画全体の売ることは考えなければいけないんですが、1番は真摯に映画と向き合うってことだと思うんですよね。それをどこか何々の都合でとかがよぎった。そういう自分が恥ずかしいということでしょうかね。
Q:歩み続けるために、失敗の原因を自分の中に探したのですね。
よくピンチはチャンスって言うんですけど、チャンスはピンチなんですよ。頂いたチャンスをモノにできなかったってことはアウトなんですよ。そうすると、今まで応援してくれた人がやっぱりそっぽ向くんですよ。つらいけど、それはしょうがないですよね。そこで何ができるかというと、また1から始めるしかないわけです。今は映画界全体が、やっとオリジナルの企画を始めようという流れになっていますけど、当時は原作全盛ですから。もちろん直木賞とか本屋大賞の作品は(売れていない)自分では抑えられないので、「これは!」っていうものを見つけるしかないんです。2023年3月公開の、映画『ロストケア』は企画してから10年かかったんですけど見つけて、原作者がその熱意だけで6年も待ってくださったんです。『ブタがいた教室』も13年かかったんですけど、そうした、本当に自分がやりたいものを見つけるってことですね。映画会社にはほとんど断られました。最後に日活さんが企画に乗ってくれたのが『ブタがいた教室』です。『ロストケア』も同じで、最後に日活さんが救ってくれたんですよ。Q:壁を乗り越えるためには、安易に近道を探さずに、自分で汗をかくしかないと?
そう思います。僕は「はい、あなたが演出」っていうタイプじゃなくて、自分が0から企画を見て、これをやりたいと手を挙げて、巻き込んでいく。だから、時間かかるんです。バナナの時もそうです。映画も撮ってなくて、ヒット作もない。50歳も過ぎている中で、前から知り合いの松竹のプロデューサーから「どうするんですか、あなた」って。「30個、原作やマンガ、リメイクの企画を出してください」って言われて30個出したんですが、出した企画がかっこいいものばかりだったんでしょう、「何かっこつけてるんですか」って言われました。その時に、その方が「人を感動させてなんぼの世界でしょ」って言ってくれたんです。僕は感動って言葉が嫌いで、心を揺さぶりたい。同じ意味なんだけど、感動とか泣かせたいとか言われると、これ見よがしのものは作りたくないっていう思いがあったんですが、「そんなかっこつけてどうするんですか」「もういいっていうぐらいまで泣かしていいんじゃないですか」って言われたんです。Q:その一言で、前田さんが本当に撮りたい作品を見つめ直すことが出来たと?
「何かっこつけてるんですか」って言われたときに、『こんな夜更けにバナナかよ』を思い出したんです。それまでは、タイトルが気になっていて原作を買っていたのですが闘病記ものとかがなんかいやだなと思っていて、ずっと(原作を)読んでなかったんです。ただ、その言葉がきっかけで読んだら、単なる闘病記ものじゃないし、もっと言うと障がい者っていうものに対する概念が、全て取っ払えるような力強いものだったので、これを映画化したいと思ったんです。松竹のプロデューサーに話をしたら読んでくれて、「これをやりましょう」と、「ただし3年かかると思います。その覚悟はありますか」って。もう失うものはないので、「何年かかってもやりたいです」と。実際3年半かかって、映画化することができました。前田さんの「THE WORDWAY」。次回♯2は、転機となった「こんな夜更けにバナナかよ」のヒットの裏側に迫ります。数々の失敗を経てたどり着いた監督に求められる資質、作品に込めた思いとは―。
 THE WORDWAYでは、読者から、アチーバーの記事を読んだ感想を募集しています。記事を読んだ感想、「昨日の自分を超える」トリガーになったこと、アチーバーの方々に届けたい思いなど、お送りください。いただいたメッセージは、編集部から、アチーバーご本人に届けさせていただきます! アチーバーに声を届ける
THE WORDWAYでは、読者から、アチーバーの記事を読んだ感想を募集しています。記事を読んだ感想、「昨日の自分を超える」トリガーになったこと、アチーバーの方々に届けたい思いなど、お送りください。いただいたメッセージは、編集部から、アチーバーご本人に届けさせていただきます! アチーバーに声を届けるPROFILE
-
◆前田哲(まえだ・てつ) 東京東映撮影所で大道具のアルバイトを始めて、セット付き、美術助手を経て、フリーの助監督として伊丹十三、滝田洋二郎、大森一樹、崔洋一、阪本順治、松岡錠司、周防正行らの作品に携わり、1998年相米慎二総監督のもと、オムニバス映画『ポッキー坂恋物語 かわいいひと』で劇場映画監督デビュー。主な作品に『ドルフィンブルー フジもういちど宙へ』(2007)、『ブタがいた教室』(2008)、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』(2018)など。2009年度より、東北芸術工科大学デザイン工学部映像学科准教授を務め、2013年に退任。2021年には『老後の資金がありません!』『そして、バトンは渡された』で報知映画賞監督賞
を受賞。2023年は『ロストケア』『水は海に向かって流れる』『大名倒産』が連続公開。次回作は、直木賞をはじめ数々の賞を受賞し、今年11月5日に100歳を迎える作家・佐藤愛子氏のベストセラーエッセイ集を実写映画化した「九十歳。何がめでたい」。女優・草笛光子が自身と同じ90歳の作家を演じる話題作で、24年6月21日公開。
HOW TO
THE WORDWAYは、アチーバーの声を、文字と音声で届ける新しいスタイルのマガジンです。インタビュー記事の中にある「(スピーカーマーク)」をクリック/タップすることで、アチーバーが自身の声で紡いだ言葉を聞くことができます。 CATEGORY
Top Achievers from other areas are also on the way. Stay tuned!! IMPRESSIVE WORDS
-
◆前田哲(まえだ・てつ) 東京東映撮影所で大道具のアルバイトを始めて、セット付き、美術助手を経て、フリーの助監督として伊丹十三、滝田洋二郎、大森一樹、崔洋一、阪本順治、松岡錠司、周防正行らの作品に携わり、1998年相米慎二総監督のもと、オムニバス映画『ポッキー坂恋物語 かわいいひと』で劇場映画監督デビュー。主な作品に『ドルフィンブルー フジもういちど宙へ』(2007)、『ブタがいた教室』(2008)、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』(2018)など。2009年度より、東北芸術工科大学デザイン工学部映像学科准教授を務め、2013年に退任。2021年には『老後の資金がありません!』『そして、バトンは渡された』で報知映画賞監督賞
RECOMMEND
あわせて読みたい
-
-
-
「大事なのは作品であって、自分の個性や作家性なんてどうでもいい」
前田哲 #2
-
-
-
-
「悩む時間があるって事は、行動する時間が残っているって事」
鈴木 啓太 #2
-
-
-
-
「『言葉は大事。夢は叶う。比べるのは昨日の自分』 そう言い続けてきた」
矢野燿大 #1
-
-
-
-
「気持ちのままに突き進むことで、行動がついてきたり、変わってきたりする」
上田桃子 #1
-
-
-
-
「やり続ければコミュニケーションが増える。コミュニケーションによって言葉、経験、友達が増えていく。それが人としての潤いになる」
山田幸代 #1
-
-
-
-
「明日の方が良い芸をしていたいから、毎日「今日は初日」と思ってやってきた」
オール巨人 #3
-
-
-
-
「こだわりを通して仕事にしたいのなら、人の倍やらないと成立しない」
梅原大吾 #3
-
-
-
-
「人生という時間軸で見れば、失敗は単なるスパイスでしかない」
鈴木 啓太 #1
-
-
-
-
「良い組織を作るためには、足を引っ張り合う悪い群れには共感しない」
竹下佳江 #2
-
-
-
-
「1つずつは飛び抜けた力が無くても、掛け合わさった瞬間に希少な存在になる」
髙田春奈 #3
-
-
-
-
「羽生さんも、藤井さんも、頂点にいる方ほど貪欲に次のステップに進もうとしている」
深浦康市 #2
-
-
-
-
「『ここだけは絶対に負けない』という強いものがあるから、他の事で負けても悔しくない」
澤 穂希 #1
-
-
-
-
「どうせ立ち向かうなら、楽しく立ち向かう。筋トレと同じで、つらい環境が筋肉になる」
楠本修二郎 #3
-
-
-
-
「失敗や挫折、苦悩の連続の中に、一瞬の成功を勝ち取っていくこと」
井上 康生 #3
-
-
-
-
「結果が出ないことをメンタルのせいにしているから、同じことを繰り返してしまう」
青木宣親 #1
-
-
-
-
「成功をつかみとるためには、自分が求めるキャリアを分析し、戦略を立てていく」
近藤豪 #1
-
-
-
-
「本物を見て、本物を真似て、本物の考え方や経験を自分の経験に照らし合わせることが、成長を加速させる」
山田幸代 #2
-
-
-
-
「チーム全員でアウトプットして作った目標なら、全員でそこに向かっていける」
大神雄子 #3
-
-
-
-
「誰かが通った道は歩きやすいが、何も残っていない。誰も通っていない道は歩きにくいが、多くの世界がある」
羽根田卓也 #2
-
-
-
-
「100発100中は無理。勝ちたい数があるなら、それと同じ数だけ負ければいい」
姫路麗 #2
-
-
-
-
「選択の正誤はその場では出ない。決まるのはその先。だから、決断自体は大したことではない」
村田諒太 #1
-
-
-
-
「自分の人生観みたいなものを大事にすることが、結局はゴルフに繋がる」
上田桃子 #3
-
-
-
-
「「取り組み方」と「考え方」が1日の流れを決める。それが1年、2年後につながっていく」
青木宣親 #2
-
-
-
-
「常に「普通」でいる。うまくいっているから偉そうにするのは愚かだし、今がだめでも卑屈になる必要はない」
梅原大吾 #2
-
-
-
-
「チームは盆栽と一緒。毎日きれいにカットしなければ、おかしくなる」
トム・ホーバス #2
-
-
-
-
「自分だけがいい思いをしてはいけない。師匠、先輩から受けた恩は後輩に返せばいい」
岩澤 資之 #3
-
-
-
-
「何かを頑張ろうと思った時に、頑張るスイッチが押せる自分の状態だったらいい」
上田桃子 #2
-
-
-
-
「三振は三振でいいけど、見逃し三振だけはしたくない」
ハリウッドザコシショウ #1
-
-
-
-
「寝る前に鏡を見て、「自分の力をすべて出したか」と聞く。それに答えられないのなら引退した方が良い」
トム・ホーバス #3
-
-
-
-
「変わり続けても変わらないものを守っていこうと思っている」
西高辻󠄀 信良 #1
-
-
-
-
「何か物事を達成したければ絶対に諦めない」
青木宣親 #3
-
-
-
-
「テープを切ったことの意味を噛み締められる人は、次の目標も勝手に出てくるはず」
真山 仁 #2
-
-
-
-
「本当の自分はこうじゃないと思っても、勝つため、自分が上に行くために変えないといけないこともある」
竹下佳江 #1
-
-
-
-
「行動をまず変えないと、変わらない」
澤村拓一 #3 (メジャーリーガー)
-
-
-
-
「『日々成長』―。何か成長したければ、結果失敗しても、最終的にたどり着きたいゴールには近づいている #4」
上田桃子 #4
-
-
-
-
「結果を変えるためには、自分の弱みを受け入れ、ストロングポイントで戦うこと」
深浦康市 #1
-
THE WORDWAY ACHIEVERS
隔週月曜日に順次公開していきます
IMPRESSIVE WORDS
LATEST WORDS
最新の記事
-
-
-
「何か物事を達成したければ絶対に諦めない」
青木宣親 #3
-
-
-
-
「「取り組み方」と「考え方」が1日の流れを決める。それが1年、2年後につながっていく」
青木宣親 #2
-
-
-
-
「結果が出ないことをメンタルのせいにしているから、同じことを繰り返してしまう」
青木宣親 #1
-
-
-
-
「アピールは成長のために必要。出会う人の数が増え、新しいことを知るチャンスも増える」
田中史朗 #3
-
-
-
-
「言葉に出すことはすごく大事。言葉で相手を引っ張ってあげることもできるし、しんどさを楽しさに変えてあげることもできる」
田中史朗 #2
-
-
-
-
「「もう無理」と思っているところから、自分で何か良い部分を見つけ出して成長し、そして限界を突破する」
田中史朗 #1
-